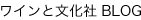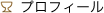2017.07.01
「もっと女性たちの声に耳を傾けてください。法律をくぐりぬけて彼女たちは妊娠中絶をしているのです。・・・若い未婚の女性たちのことを言っているのではありません。4-5人と子供たちを育てなければならない母親たちにとっては更なる負担を強いているのです。・・・」
1974年9月、国会は騒然とした。同じ保守党の男性議員からもヤジが飛ぶ。「堕胎をさせるならナチと同じ方法でやれ! 」その議員はシモーヌ・ヴェイルがかつてアウシュビッツの強制収容所に送られていたことを知らなかった。その後、すぐに彼は謝罪をした。そして同年11月、皮肉にも野党の賛成で妊娠中絶法、いわゆる『ヴェイル法』は成立した。女性たちの権利が認められた瞬間だった。
男性議員がほとんどだった当時のフランスにおいて女性の権利を主張し、それを守ることに敢然と戦い続けたシモーヌ・ヴェイル。フランスの国民からもっとも愛され尊敬された女性だった。そんな彼女が昨日、89歳で逝った。ひとつの時代が終わった。アカデミー会員でもある作家ジャン・ドルメッソンがシモーヌ・ヴェイルがアカデミー会員として迎えられ時に贈った言葉がタイトルの言葉である。『勇気ある女性』、それがもっとも彼女を表す形容詞であることは間違いない。心からご冥福を祈りたい。
写真 1974年、ジスカルデスタン大統領政権下、厚生大臣を務めていたシモーヌ・ヴェイルはヤジ・誹謗・中傷・罵倒が飛び交う中、女性の権利を守るために命を懸けて戦い続けた。そんな彼女の有名な国会での演説のシーン。昨日、仏の全テレビ局はシモーヌ・ヴェイルにオマージュを捧げた。