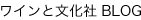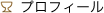2015.07.08
パリの国立美術館、グランパレで8月3日まで『ジャンポール・ゴルチエ展』が開催されている。”ファッション界の恐るべき子供” ( l’enfant terrible de la mode )と70年代当時、メディアは一斉に彼のことをこう称えた。1971年から2015年までの代表的な作品や彼が手がけた映画・舞台衣装など、まさに” 恐るべき稀有な才能” が炸裂したこの展覧会に圧倒された。
「ファッションショーというものが存在しなかったら、多分デザイナーにはなっていなかった」という彼の言葉が如実に語っているように、ゴルチエはショーという総合芸術が持つそのスペクタクル性に大いにこだわっていたのだろう。会場中央には舞台を設けてファッションショー形式で次々に代表作品がマネキン人形に着せられて登場する。その周りには実在のセレブ達がまるでその場にいるかのように配置され、ファッションショーの臨場感を醸し出している。そんな演出にもゴルチエの遊び心がふんだんに発揮されている。
中でもゴルチエらしさといえば女性のコルセットだ。かつてマドンナが舞台で乳房を必要以上に強調するコルセット姿の衣装で現れた時には会場は大いに沸いたものだ。しかしゴルチエにとっては女性の体を締め付けるはずのこの”道具”を逆手にとって、まるでジャケットのように身につけさせているところに彼らしいユーモアが表れている。しかし、それはやがて人間の肌にまで言及し裸とかエロティシズムといったもの、あるいはタトゥー(今では当たり前のアート感覚だが当時としてはかなりタブーでスキャンダラスなものだっただろう) のようなボディーアートまでをもファッションのテーマとしてしまうゴルチエのギャグのような感性に時代の異端児感は否めない。しかし、そんなものも人間の性としてより一層肌に寄り添うような特殊な素材をふんだんに使って身体をテーマに表現。それはプレタポルテの世界だけではなく、オートクチュールといった高貴な世界にまでそのテーマが堂々と表れている。しかし、それは決して下品にはならず、むしろ職人の手仕事(そんな服に取り組んでいるときの職人たちの表情は多分生き生きとしていたことだろう!) にはため息が出てしまうほどの高度な技術がちりばめられている。
最後は”アーバン・ジャングル”と名ずけられた一連のコレクションだ。ゴルチエはことごとく”違い” というものにこだわる。それは宗教であり文化であり素性といった自分らしさ。ユダヤ教ラビが身に着けていた重たいコートや円形の帽子、ゴビ砂漠の過酷な自然のなかで着用するモンゴルの革の防寒コート、フラメンコの踊るような裾の長いスカート、芸者を連想させるキモノ、そして真っ白い透き通った素材を何重にも重ね合わせたドレスにはアフリカの土着民族の仮面がリリーフ状に浮き出ている・・・。まさに今回の展覧会で、否、彼のライフワーク全体のなかでゴルチエが一番表現したかったのは、こうした民族の差異・アイデンティティーではないだろうか。しかし、そういったものがミックスされハイブリッドされることによってまた新たな文化が生まれてくる。21世紀とはそういった時代、自分らしさをクリエイトできる時代なのだというゴルチエのメッセージ。そんな彼の人間性に大いに感動した。それは衣服という人間ならば誰しもが着用する日常性の中に、これだけの壮大なテーマが潜んでいることを私はゴルチエから教わったような気がした。素晴らしい展覧会だ。
写真 ピエール&ジルによるゴルチエの肖像画。トレードマークでもあるブルーのストライプのマリニエールは「ストライプの持つグラフィカルで構築的な部分が好き」と言う。ファッションショー形式で次々に目の前に現れてくるコレクション。素肌を意識した素材がふんだんに使われている。女性のコルセットからイメージしたフェティッシュな世界観や心臓という臓器までもアートにしているそのユーモアが可笑しい。民族の違いや宗教の違いといった人とは異なる自分らしさというものを衣服で表現しているところにゴルチエのメッセージが受け取れる。ゴルチエ自身のマスコット人形、グランパレのファッサード――こんな重厚な歴史的モニュメントの中でアバンギャルドなゴルチエワールドが炸裂するのがパリという街だ。