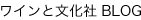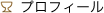2012.06.20
「すべての食物は思考する価値のあるものである」とはフランスの社会人類学者クロード・レヴィ=ストロースの言葉だが、食べることはやっぱり人間の営みの中では最も楽しいものだということに最近、つくづくと思い当たるようになってきた。いくら最新のファッションに身を包んでも下半身にたっぷりとついた贅肉では絶対にステキに見えるはずもないし、衰えた体力ではどんなに頑張ってもアスリートにはなれない。そうなると人生消去法でいくと残るのはただただ食欲を満たすばかり。でもお腹がいっぱいになれば何でもいいという訳ではない。こだわりとか、どうやって食べればおいしいかとか、季節感のあるものを食べたいとか、いろいろと考えていくうちに、結構食べることって知的好奇心をくすぐってくれるものであることに気づかされる。それが冒頭の言葉に思い至った次第である。
今パリの民族博物館「ケ・ブランリー美術館」では『口蓋の誘惑―中国における調理をすること、そして食べること』展が開催されている。世界の三大料理といえば「中華料理・フランス料理・トルコ料理」と言われたものだが、その賛否は別としても中華料理が世界中を席捲しているのは間違いない。どんな僻地に行っても中華料理屋の看板がないことなどあり得ないし、中華料理を食べたことのない人なんて日本料理を食べたことのない人の割合に比べたら微々たるものだ。そんな中華料理のルーツを器や道具を背景に掘り下げてみようと試みているのがこの展覧会だ。
紀元前7000~2000年、新石器時代の生食から加熱食にはじまり、1644~1912年、満州族の最後の王朝、清の時代の華麗なる料理文化に発展するまでの軌跡を辿っている。なかでも「水」の登場は蒸し料理や食物を清潔に浄化させることの意味をもたらしてくれたり、唐の時代には果物をはじめとする、それまで食卓にのぼったことのない新食材がたくさん入ってきたことで飛躍的に食文化が発展した歴史などなど、興味は尽きない。最後の皇帝、紫禁城では何と6000~9000人近いひとたちが一日12000食もの料理を作っていたというから、そのスケールたるや、やっぱり中国はでっかい。
展覧会の最後を飾るのが7人のアーチストによるユニット”PLEIX”が制作したビデオ。中華料理の回転テーブルからイメージしたそのビジュアルは、まるで水車のようにくるくる回る皿が次から次へと交錯しては消えていく。その鮮やかな色の美しさや精巧な構成には思わず目を奪われる。現代の中国をイメージした赤の漆のテーブルや、どぎつい大輪の花、盛りだくさんの料理といったように大量の消費社会に生きる現代人の矛盾をテーマにしている。
写真 広告制作を多数手掛けているアーチスト集団PLEIX、その緻密な仕事は世界中の数多くの賞を総なめにしている。