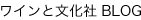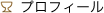2012.03.15
来週、ストラスブルグで行われるプロのための料理見本市「EGAST」でデモンストレーションをするために来仏された神戸の料理人、『京料理 たか木』のオーナーシェフの高木一雄さんがパリのフレデリック・シモナンさんの厨房をたずねた。昨年、初めて来日したシモナンさんは以来、大の親日家になってしまったが、滞在中から特に豆腐に興味を抱いていた様子。その話を高木さんにお伝えすると「では豆腐は豆腐、似て非なる”ゴマ豆腐” を指南しましょう」と相成ったのである。
当日は初対面とは思えないようなフレンドリーな雰囲気。「君の厨房だと思って自由に使ってもらって構わないよ!」というシモナンさんの言葉に高木さんもリラックス。昆布とカツブシの出汁をとるところからスタートした。高木さんは普段、神戸でも子供たちに出汁の味を知ってもらおうと小学校に出向いて食育のボランティアをやっている。一方、シモナンさんもパリの小学校で子供たちに様々な食材の味を知ってもらおうと積極的に活動している。そんな二人は3児の父親というところも同じ(しかも、二姫・一太郎も同じ! ) 相似点の多い二人だけに息もぴったり。約一時間かけてのデモンストレーションは熱いうちに終了。
翌日、早速シモナン流一皿が出来上がり。「クロベット・グリーズと呼ばれる小エビにブラックラディッシュとシブレット、シソの葉っぱに黒ゴマという演出。もちろん出汁をブイヨンに見立てて温めてサービス」。こんな夢のようなコラボレーションがすぐに完成してしまう。やっぱり料理人の世界は言葉なんかいらないんだとつくづくと感じた。
写真 シモナンさんと高木さん、初対面とは思えない息の合ったコンビ。シモナン流「ゴマ豆腐」の一皿。