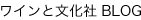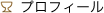2010.10.12
“フランス東部のロレーヌ地方出身のひとりの男がパリジャンになった。しかしキッシュロレーヌもミラベル(すもも) も決して忘れることはなかった。これはひとりのジャーナリストの物語。彼は世界中のほとんどの料理を食べつくした。そして辿り着いたのはフランス料理が一番だと。料理に生涯を捧げ、インディペンデントのコラムニストとして、地球にやさしく、世界中の味がスタンダード化されることにもの申し、ビオと喜びを愛し、スローフードの理念「美味しい・やましさのない・正当性」を継承する・・・” と、裏表紙に書かれている。
『僕の辿ってきた食の道』(Mes chemins de table : hoebeke出版) 、そんなタイトルの本をつい最近出した我が友人、JPGENEの出版記念パーティーに駆けつけた。以前、”すごくおいしいビストロがあるから”とランチを誘ってくれた「ラシーヌ」という店の軒先を借りて、わざわざナンシー( 注 ロレーヌ地方の県庁所在地 ) から取り寄せたという「パテ・ド・ロレーヌ」と「ベルガモットのキャンデー」が振舞われた。
Le Monde Magazineに毎週、辛口だけど滅茶苦茶まっとうな食のコラムを書き続けて早7年、リベラシヨン、アクチュエル、ル・マタン・ド・パリ、ル・ヌーヴェル・オプス、ジェオ、ル・ポワン、レクスプレス、マリアンヌ、エールフランス・マガジン・・・・、見事なまでのその筆の冴えは右から左、中道派まですべての読者をひきつける。「終戦直後に生まれた僕は、当時やっと配給生活が終わったところ。教師の家系に生まれながら、僕だけがその系譜をたどらなかった。それは、もうスキャンダル! 貧しい生活のなかにも毎年庭でとれたミラベルを摘んで家族みんなでテーブルを囲んで分けあった。それが僕の原点」だと話してくれる。リベラションでは政治記者として鳴らした。しかし、ふとしたことでジャック・マキシマン(注 ロブションやデュカスと並ぶ超有名なグランシェフ) と知り合い、彼の厨房で2週間、料理の手ほどきを受けて料理に開眼。以来、食のコラムニストになった。
上着のポケットにさりげなく「Le Monde」紙を無造作に突っ込み、顔写真を撮られることをぜったいに拒む(食のジャーナリストはみんなそう! )、なによりもビンビン尖った議論好き。いわゆる一昔前にいそうなフランスの典型的左翼インテリジェントだ。考えてみれば私が70年代の中ごろに最初にパリにやってきた頃は、そんなフランス人が巷にゴロゴロしていたように思う。世界のグローバル化とともに世の中がスタンダード化されて、こんなフランス人も希少価値になりつつある。絶滅品種ならぬ、絶滅人種にならぬよう自分たちのアイデンティティーはしっかりと守りたい、そんなことを考えさせられた夜だった。
写真 ロレーヌ産パテとベルガモット・キャンデー、著書にサインするJPGENE